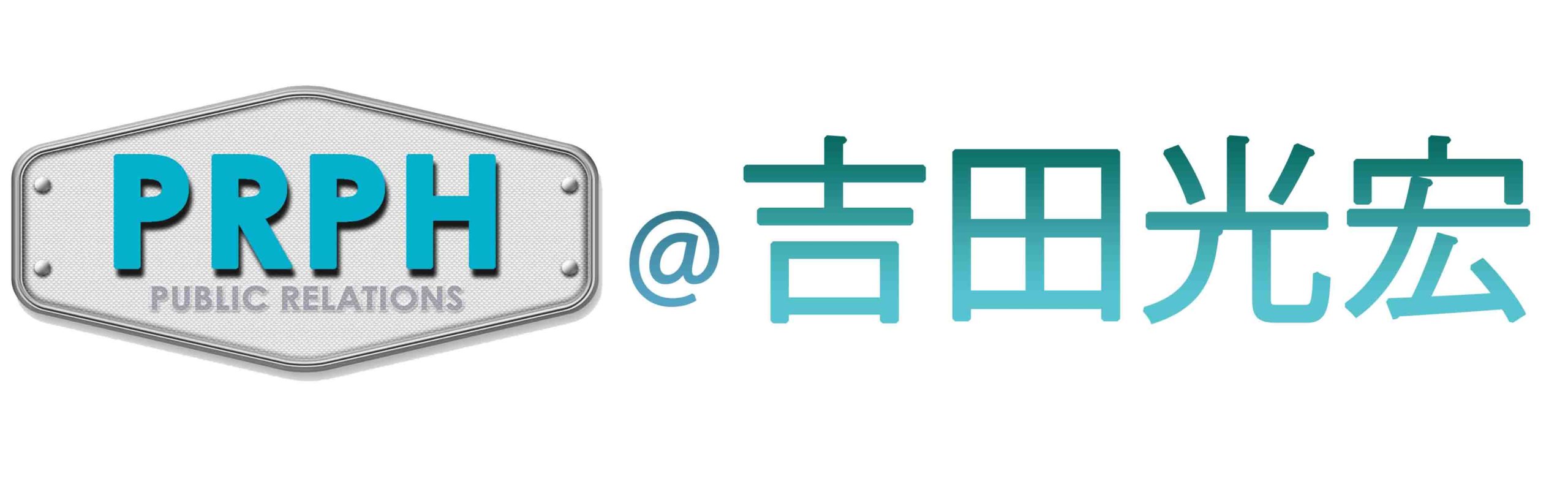彦根城で井伊直弼の生涯を思う
3度目の彦根城。天守閣に登ったのは2度目だった。「井伊直弼の城」について詳しくは知らなかったが今回改めて城の「立派さ」を知った。また、幕末の混とんとした情勢の中で、直弼がどのような思いだったのか、想像を膨らませた。

彦根城天守
彦根城は1622(元和8)年に完成、明治初期の廃城令で取り壊されそうになったが、明治天皇の意向があって中止されたという。江戸時代以前に建てられ現在まで残っている12城の一つ。うち国宝は5城で、彦根城のほか、姫路城(兵庫県)・松本城(長野県)・松江城(島根県)・犬山城(愛知県)。
10年前の2回目の訪問は雪景色の中。城は観光客も少なかったし、ひこにゃんもいて満足した。琵琶湖が見渡せ、西国の押さえとして重要な城であったことが分かった。今回は西の丸三重櫓、井伊直弼生誕の地である槻(けやき)御殿、国の名勝「玄宮楽々園」、彦根城博物館なども探訪した。

玄宮園
彦根藩第15代藩主の井伊直弼は幕府大老を務め、日米修好通商条約の調印を断行した。条約調印を巡って反対派の弾圧(安政の大獄)や開国路線を推し進めたことで、多くの反発を受け桜田門外の変で暗殺された。この辺りは教科書の通り。
吉田松陰や橋本佐内の墓がある南千住の回向院や萩などいろいろ訪れた際に、桜田門外の変で暗殺されたのも仕方ないと思ってきた。
直弼の人物像を語るには物足りないが、今回注目したものを挙げてみよう。
暗殺される2カ月前に描かれた肖像画に添えられた歌
あふみ(淡海・近江)の海 磯うつ浪の いく度か 御世にこころを くだきぬるかな
(琵琶湖の波が磯に打ち寄せるように、世のために幾度となく心を砕いてきた)。幕府大老として国政に力を尽くしてきた心境をあらわしている。
玄宮園近くにある銅像の隣に置かれた歌
一身に責負いまして 立ちましし 大老ありてこそ 開港はなりぬ
井伊文子
井伊文子さんは直弼の孫の妻。銅像は、明治時代に旧彦根藩士らが井伊直弼の遺徳を顕彰するために建立した。

井伊直弼公銅像
辞世の句。
咲きかけし 猛き心の一房は 散りての後ぞ 世に匂ひける
(咲きかけた桜のように 私が下した大決断は、私の死後にかぐわしく匂って、その良さを知ることになろう)
襲撃前日に自らの心情を書いたものが辞世の句とされている。暗殺されることを予感していたのかもしれない。
このところ読む本は、幕末維新のものが多い。幕末の勘定奉行・川路聖謨(としあきら)の生涯を描いた『落日の宴』(吉村昭)、長編歴史小説『桜田門外ノ変』、幕末幕政の中枢を担った小栗忠順(ただまさ)を描いた司馬遼太郎の『十一番目の志士』などなど。徳川幕府の「末期症状」の中で、有能で志の高い人物たちの波乱の生涯が見えてくる。
小栗の場合、2027年の大河ドラマ『逆賊の幕臣』に決まったので、再評価の機運が高まるだろう。天才肌のエリートで、激動の幕末に幕府の要人として活躍。日本初の遣米使節になるなどの功績が多くある。勝海舟のライバルと言われた人物。
今年3月に横須賀の臨海公園で胸像を拝み、群馬県高崎市にある東善寺の墓を訪ねた。近くの川沿いにある処刑の場にある記念碑には「ザ・歴史」のインパクトを感じた。
本を読んで、史跡を訪ねても、持ち合わせている情報は、歴史のほんの一部。それでも現場に足を運んで、そこの空気を嗅げば、ちょっとだけ深層に迫れるのでは。そうした知識はPR支援や他の執筆に役立つのでは…。そんな気がしている今日この頃である。