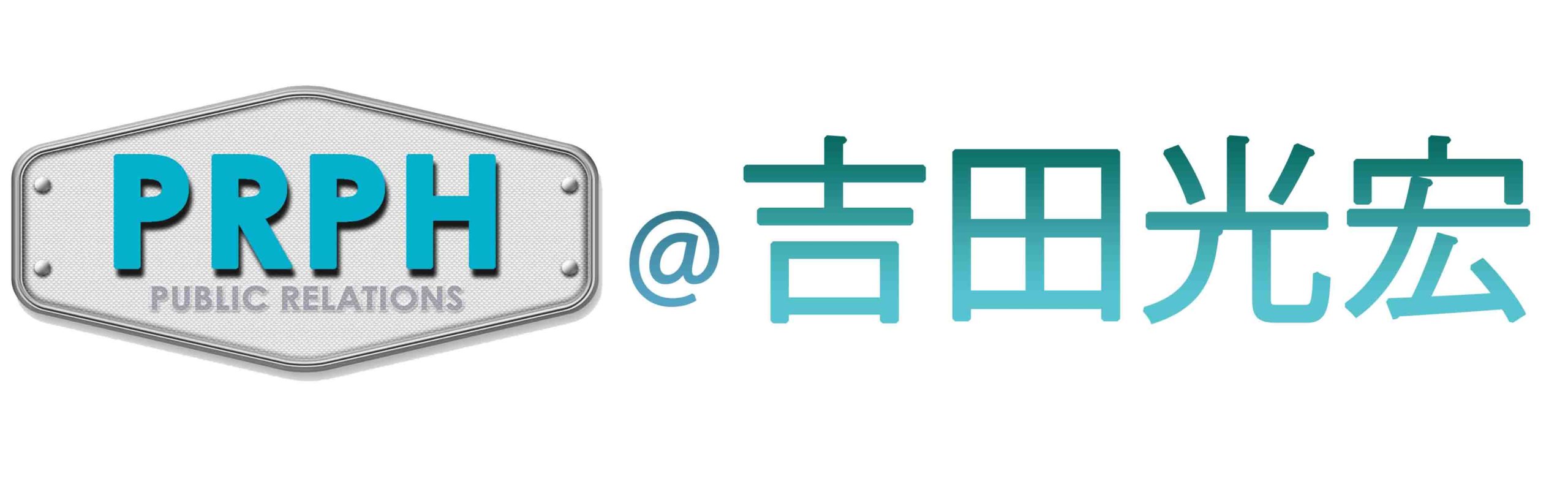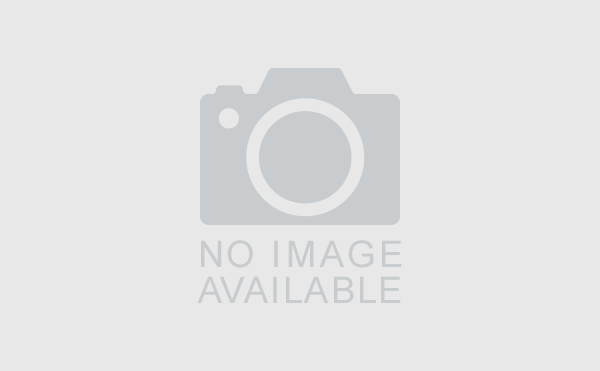沿岸を歩く…取材スタートの長崎は今日も雨だった
7月24-25日の期間、月刊環境情報誌『グローバルネット』の連載「日本の沿岸を歩く 海幸と人と環境と」の取材で長崎県を訪ねた。
取材テーマは「かんぼこ王国」、「平戸漁業体験」「九十九島のいりこ」。長崎市から取材を始め、その後は西彼杵(にしそのぎ)半島を北上、平戸で定置網の漁業体験、そこから南に戻って佐世保市の九十九島漁協を訪ねた。

皿うどん
長崎市に到着した午前中は小雨、午後からは曇り。長崎新地中華街で長崎に来ると必ず食べる皿うどんを味わった。そこに入っていた赤と緑の蒲鉾の正体を知ったのは、「かんぼこ王国」のインタビューであった。
長崎は歌の似合う街だ。
長崎は今日も雨だった 内山田洋とクールファイブ
https://www.youtube.com/watch?v=YGfseX5WdVE
長崎から船に乗って 五木ひろし
https://www.youtube.com/watch?v=btUS1fOV3X8

新長崎漁港
水産県の拠点、新長崎漁港 に着くと港の中を見て回った。以前ナマコとカブトガニ事情を取材した長崎県の水産試験場もある。
「長崎かんぼこ大国」について長崎蒲鉾水産加工業協同組合で話を聞いた。「かんぼこ」は水産練り製品全般を指し、ブランド化を進めている。長崎ではかまぼこは「おかず」として食べられることを知った。近くのスーパーを覗いてみるとあるわ、あるわ…。
長崎蒲鉾水産加工業協同組合のすり身工場。同じようなすり身製造は国内で北海道に5社ほどあるだけで、他はここだけと聞いた。長崎周辺で捕れた魚を原料にしてすり身を製造し、全国各地のかまぼこ業者に供給している。あなたが昨日食べた、かまぼこの原料かも知れない。
近くのスーパーに入ってみると、長崎新地中華街で食べた皿うどん に入っていたかまぼこ(ハンペン)を発見。さらに長崎ちゃんぽん麺とナポリタン を合わせた新名物料理「ちゃポリタン」にも巡りあった。

ながさきサンセットロードの標識
長崎から平戸を目指して西彼杵(にしそのぎ)半島の「ながさきサンセットロード」(国道202号線)を北上した。車の通行量は少なく、海岸線の素晴らしい風景を独り占めだ。
国道202号 は長崎県内でも屈指のフォトスポット。角力灘 から五島灘 へ続く海原は雄大だ。
遠藤周作文学館 の入り口があった。小説「沈黙」の舞台に立つ。愛用品、遺品、生原稿などの資料がある。遠藤はクリスチャン、この地もキリシタンの里として知られる。

西海橋と新西海橋(手前)
西彼杵(にしそのぎ)半島と佐世保の間に架かる西海橋と新西海橋(手前)。1955年に開通した西海橋は全長316m、「東洋一のアーチ橋」と称された。2006年、北側に平行して新西海橋が完成した。
橋の下は日本三大急潮の一つ伊ノ浦瀬戸。この橋を渡るときはいつも「西海ブルース」を歌ってしまう。西海→再会を連想させる昭和の名曲。
西海ブルース 内山田洋とクールファイブ
https://www.youtube.com/watch?v=8AQOf7GPS4c
西海の丘展望台から見える3本の針尾無線塔(高さ135~137m)。約300m間隔の正三角形に配置されている。真珠湾攻撃の暗号文「ニイタカヤマノボレ」を中継したとされる。以前、別の長崎取材でこの塔を訪れ、内部を見たことがある。空っぽだった。

引揚記念平和公園
佐世保市針尾北町にある引揚記念平和公園。敗戦後、中国大陸などからの約140万人が上陸した。平和を願う公園として整備され、併設された資料館には当時の引き揚げ者の着衣、日記、リュックサックなどが展示してある。
浦頭引揚記念平和公園・資料館
https://www.sasebo99.com/spot/262
公園には、端義夫『かえり船』の歌唱碑がある。歌詞に引揚者の安どの気持ちと失意を感じる。
戦争に敗れた国家、国民がどれだけ辛く空しい思いをするのか…。世界平和だ、戦争反対だ、などと声高に語る前に、この歌を黙って聴いてもらいたい。
かえり船 田端義夫
https://www.youtube.com/watch?v=iKgPJH1b6io
夕暮れ迫る展海峰(標高166m)から望む九十九島。208の小島が浮かぶ絶景は田中穂積作曲の唱歌『美(うるわ)しき天然』の舞台となった。1902年(明治35年)完成した日本初のワルツ。
武島羽衣 の詞は九十九島や佐世保湾に関係なかったが、佐世保海軍第三代軍楽長の田中の描いたイメージにぴったりの曲となった。活動写真の伴奏、サーカスやチンドン屋の音楽として親しまれているが、詞を改めて読むと、日本の自然の素晴らしさを再認識できる。
美しき天然 島倉千代子
https://www.youtube.com/watch?v=o__JigvUPtU
美しき天然 村治佳織
https://www.youtube.com/watch?v=auMoPq-yTLY
歌詞
https://www.uta-net.com/song/38952/
平戸で早朝の漁師体験に参加した。平戸島から生月大橋を渡って漁船に乗船し、10分ほどで定置網の場所へ到着。定置網に漁船を横付けし、プロの漁師たちの手際よい作業風景を見ながら、魚の水揚げを待った。

定置網の水揚げ
いるわいるわ、小さいのからでかいのまで…。参加者は作業と記念撮影で忙しい。
定置網は環境に負荷をかけない日本発祥の漁法だ。漁師体験の定置網で捕れる魚種は約50種。漁師「これがエソだよ」、私「エ~ソぅ、本当?」。
定置網の漁獲の中には、招かざる客も。地元でバリという魚で標準名はアイゴ。背と尻のひれに毒があり、漁師に忌み嫌われている。海藻を食べて磯焼けを引き起こす犯人ともされる。

捕った魚の料理
定置網漁を終えて戻ると、捕った魚が調理されテーブルにずらり。カツオ、カンパチ、アジ、イサキ、ヤリイカ…。いただいた命、すべて無駄にしないように完食!
オランダ商館や平戸城など歴史を物語る建物や史跡が多い平戸市。朱色の平戸大橋 と海のコントラストが美しい。

漁協直販所のイリコ
平戸の後は、日本有数のイリコ生産量を誇る九十九島漁協(佐世保市小佐々町)へ。周辺はカタクチイワシの豊かな漁場がある。漁協直販所「こさざ」は高品質のイリコがいっぱい。
イリコにはカルシウム、鉄、ビタミンD、DHA、EPAなど栄養素がたっぷり。買ったいりこは酒の肴にしてポリポリかじって健康増進を図った。
佐世保市小佐々町 にある九十九島漁協 の建物。対岸から見ると周囲の環境がよく分かる。イリコだけでなく、「九十九島とらふぐ」、「ハーブ鯖」などの養殖に力をいれている。