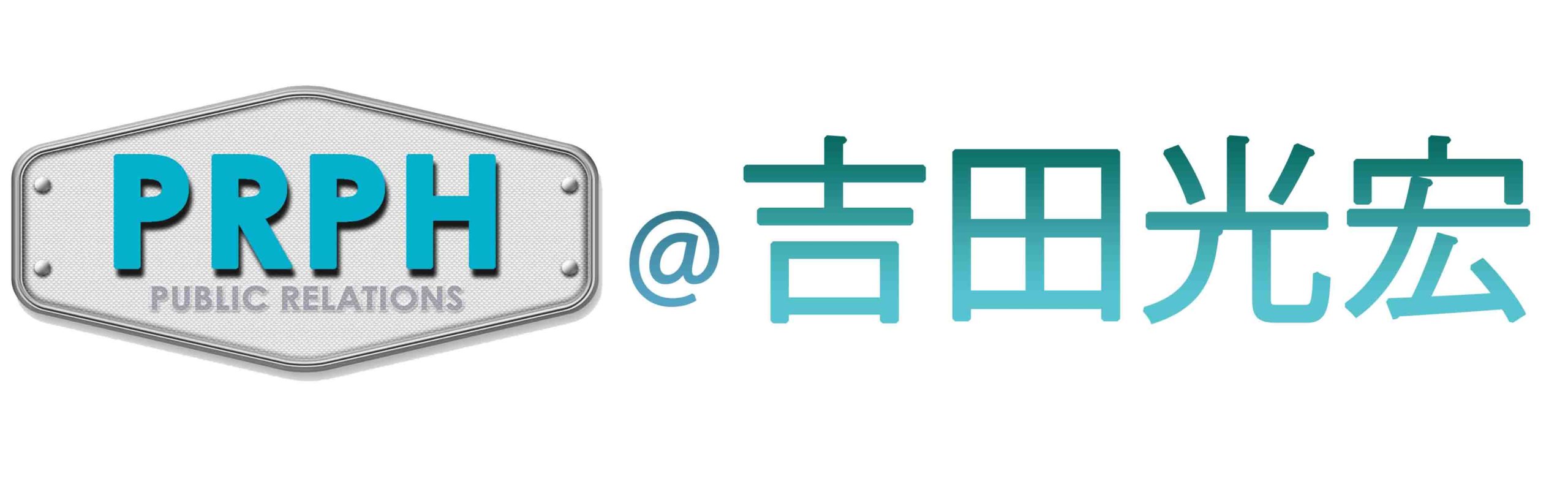豊島公害調停成立から25年
史上最大規模の産業廃棄物の不法投棄事件があった香川県豊島(てしま)。今年6月で公害調停が成立して25年になる。循環型社会への政策の転換点となった。時事通信社「農林経済」(2003年3月6日号)に寄稿したルポを一部変更して再掲する。当時の豊島の惨状は生々しく、自然環境へ影響の大きさが分かる。
瀬戸内海再生 ルポ「豊島に自然回復の兆し」
岡山県の宇野港から、目的地の香川県豊島(てしま)までフェリーで40分。船が島に近づくと、小雨交じりでかすんだ海に島影が浮かび上がった。「初めて訪れた皆さんは同じような印象を持ちます」と後で島の人から言われたように、島の西端の産業廃棄物(産廃)不法投棄現場は、島全体からすればごく一部。テレビや新聞の報道で抱いていた島全体が産廃に覆われたイメージとは違った。

豊島の西端にある産業廃棄物不法投棄現場
全国に知られる契機となった兵庫県警による強制捜査開始から13年。3年前に公害調停が成立、「豊かな島」を取り戻すために今夏から産廃撤去と中間処理が始まる。汚染水漏れを防ぐ暫定的な工事によって、最近北海岸に藻場、魚やカニなどの生物が相次いで確認された。小さな自然回復の兆しは、「元の美しい島に戻したい」と願う地元住民に希望を抱かせている。

■ポンプで汚染水循環
家浦港に着くと、すぐ目の前にある豊島交流センターを訪れた。ここには島内三地区の自治会で構成する「廃棄物対策豊島住民会議」(砂川三男代表議長)が置かれ、一連の産廃処理問題に対応している。
見学者や取材者はまずここに連絡をとって、案内や情報提供を受ける。センター管理の町職員が常駐し、住民らが三々五々出入りしている。事務所には新聞記事の切り抜きや関係ニュースなどを記録したビデオテープなどが並ぶ。スケジュール表には、個人や団体の訪問者の名前がいくつも書き込んであった。昨年は3,461人が見学や視察などで訪れたという。
1990年のテレビ報道のビデオを見ると水銀、鉛、ポリ塩化ビフェニール(PCB)、ヒ素、テトラクロロエチレンなどを検出した調査を伝えていた。翌年の番組ではどくろマークの入ったドラム缶が映し出された。これまでの経緯や島の概略を聞いた後、住民会議スタッフの前川昭吾さんに車で10分ほどの現場に連れて行ってもらった。途中は幅4mほどの未舗装の山道。「産廃を満載したダンプがこの道をひっきりなしに通っていたのですよ」。現在の静かな島の生活からは、当時の様子を想像するのは難しい。
現場は広さ約10ha。山肌を削り取ったような地形がすっぽり遮水シートで覆ってあった。シートの下には車を粉砕し金属を取り除いたシュレッダーダストなどがあり、上を歩くとふわふわしている。今年八月から始まる廃棄物撤去のため西側部分には中間保管・梱包施設、高度廃水処理施設、廃棄物専用桟橋などの建設作業が続いていた。

遮水シートで覆われた産廃
プレハブの展示室には廃棄物の断層を切り取ったものがあり、電線、ゴム、ビニールなど、ありとあらゆるものが含まれているのがよく分かる。撤去済みの現場からは昨年7月に12t、11月5日には500トンの新たな廃棄物が見つかった。

産廃の断層展示
北海岸では有害物質を含んだ汚染水が海に流れ出さないように、2000年9月から止水壁の工事が始まり、翌01年6月約360mが完成した。鋼矢板(幅40㎝、長さ18m)を何枚も打ち込み、地下水の漏洩も食い止めている。汚染水はくみ上げて、上部に戻して循環させている。雨水が入らないように覆った遮水シートの2カ所に「浸透トレンチ」と呼ばれる小さな堀があり、黒褐色の水が絶え間なく注ぎ込まれていた。

海に流出しないよう循環させている汚染水
以前は汚染水がそのまま海に流れ出し、海岸はヘドロ状で生物が生息できる環境ではなかった。この応急対策では汚染水の流出をほとんど防ぐことができるという。汚染水は夏から高度廃水処理施設で処理されることになる。
自然回復の兆しは、止水壁の工事と同じように海岸の西の方から現れた。止水壁が完成したその年の冬にはオサガニが戻ってくるとともに、ネズミハゼが数十年ぶりに姿を現した。昨年春にはアマモの中にアオリイカがブドウの房のような卵を産んだ。かつての惨状を知る島民には、うれしい生命の息吹だった。住民会議はその後も定期確認を続けている。砂浜に出てみると、海面が黒く見える藻場が確認でき、アマモも浜に打ち上げられていた。瀬戸内海のどこにでもありそうな風景だった。

生物が戻ってきた北海岸
■県内有数のノリ養殖
豊島は面積14.61㎢。東隣の小豆島の西部とともに香川県土庄町の行政区域にある。島の人口は約1,300人。中央部には檀山(標高339m)があり、西側に家浦、東側に唐櫃(からと)、南に甲生(こう)の集落がある。三百六十のため池や豊富な水源を利用した稲作、ミカン栽培、酪農、オリーブ栽培などが盛んで、漁業は沿岸漁業やノリ養殖がある。地元から産出する豊島石の加工や販売でも知られている。高度成長期を経て過疎化が進み、人口に占める65歳以上の割合も4割を超えている。
漁業を見ると、イカナゴやイカなど豊かな漁獲があったが、近年の漁獲減、魚価低迷、後継者不足などで元気を失っている。小豆島と豊島を合わせた小豆郡の10漁協は昨年1組合が解散、4組合が合併し土庄中央漁業組合となった。豊島の3漁協は、法定組合員数20人以下になった家浦と甲生が土庄中央漁業組合の支所となり、組合のまま存続したのは唐櫃だけとなった。
かつてあった漁法の多くも姿を消した。イカナゴ漁をした「こまし網」(袋待ち網漁業)は、袋状の網を固定して魚の群れを待ち受ける漁法で、2隻が組みになって行った。以前8隻あったが今はなくなった。底引き網も減って30隻が2、3隻に。ママカリ網(浮き刺し網)も家浦ではなくなり、唐櫃だけになった。実は岡山名産として有名なママカリの多くは豊島や小豆島周辺で捕れている。

ノリ採取船などが停泊する唐櫃漁港
現在豊島で採算にあう漁業はノリ養殖だけというのが実情だ。香川県のノリ生産高は全国的にも上位にあり、品質も定評がある。県内での始まりは明治期で、特定の河川尻で行われていた。1960年代に浮流式やノリ種網の冷凍保存技術が導入され、急速に発展した。豊島には家浦1軒、唐櫃6軒の計7軒の業者がいる。家浦港から歩いて数分の伊加登美夫さん方を訪れると、一見変哲のない民家の内部に全自動ノリ乾燥機が設置され、板状の乾燥ノリを量産していた。

全自動ノリ乾燥機
3人の息子さんや従業員があわただしく作業に追われていた。海側に出ると大きな活性タンクが4基ある。塩水を使って5時間ノリを洗うタンクは1基で3万5,000枚分のノリが貯蔵できる。上に登って見ると黒いノリが洗濯機の内部のようにぐるぐると渦を巻いていた。
伊加さんは86年に機械化し、年間10万枚を生産している。現在採取六人、加工場11人で切り盛りしている。不作の今年は違うが、例年だと収穫の始まる12月から翌年の2月までは1日4、5時間しか眠れない日が続くという。
旧家浦漁協では8軒のノリ業者がいたが、次々に廃業し伊加さんだけが残った。その分伊加さんの割り当て養殖面積が拡大し、現在は1,200m×600mと周辺では最大となっている。底引き漁をしていた父親から独立して16年。億単位の初期投資などに苦労してきたが、やっと軌道に乗ってきたという。これまで県内でトップクラスの品質もキープしている。「3人の息子が手伝ってくれるので、張り合いがある。これからも頑張りたい」。66歳の伊加さんの顔がうれしそうだった。
一方、唐櫃漁協ではノリ業者6軒のうち、1軒を除いて後継者がいる。この組合のノリの生産量は、県漁連の中でも淡路島に次いで2番目。一網当たりの生産量は県内一と、優秀な品質を誇る。価格表を見せてもらうと平均値より4-6割も高い単価がついている。豊島や小豆島周辺から岡山県にかけての海域はノリの好漁場で、その中でも条件に恵まれているという。だが、今年は少雨が原因で塩分過多になり、生育がよくなかった。通常は3月まで採取するが、今年は2月上旬で取り止めた業者も多い。
■ダム建設の影響危惧
ノリ業者にとっては、90年の兵庫県警の摘発に端を発した「事件」の記憶は今でも生々しい。製品に付けられた「豊島海苔」はすぐに消え、別の名前になった。風評被害に当時は「もう一枚も売れなくなってしまうのか」と皆が心配したという。現在でも「豊島」の名前は復活していないが、関係者の間では豊島産ノリの品質が飛びぬけていることはよく知られている。
唐櫃漁協の組合員は108人(正54人、准54人)。うち90日以上操業しているのは半数ほどという。漁港にはノリの採取船や漁船が係留してあった。かつては春先のイカ漁やタイラギの潜水漁が盛んに行われていた。潜水漁はタイラギが捕れなくなって廃れ、潜水工事へ移った。その数は15、6隻という。他にコギ(底引き)が3隻、たて網が10隻ほどある。
ノリを生育させる栄養分は川から流れ込み、対岸の岡山県の吉井川からの流入が大きく影響しているという。台風や大雨で吉井川が増水すると、周辺海域の海の色が変わる。漁港にいた漁業者の一人は「吉井川の上流に苫田ダムが出来たら、ノリは今までのようにはできなくなるだろう」と岡山県の方角に目をやった。
ハマチ養殖も産廃不法投棄で甚大な影響を被った。処分場の沖でハマチの養殖をしていた家浦の安岐正三さんは、風評被害のために96年に漁業をやめた。公害調停が始まった94年12月から翌年7月にかけて国の実態調査の結果、重金属、有機塩素など有害物質を含んだ廃棄物が50万tあり、汚染水が海に流出していることが明らかになったのだ。
越年でハマチ、タイ、チヌを養殖し、規模は3万匹だった。汚染水が流出する北海岸の先に自分の養殖場があったので「いったん養殖をやめて海をきれいにすることに全力を傾けることにしました」。21年間携わってきたハマチ養殖に対する漁業補償はなかったし、申請しようとも思わなかったという。
ハマチ養殖発祥の地として知られる香川県。安岐さんは豊かな海を生かして健康でおいしい魚を育てようと努力してきた。汚れを食べるカワハギを「掃除係」としていけすに入れ、環境への配慮も忘れなかった。何度かの赤潮被害を乗り越えて顧客も付き、やっと事業が軌道に乗ってきたところだった。
東海大学海洋学部水産学科を卒業後、南米のエビトロール船や現地の駐在員になったがオイルショックで2年後には帰国。ハマチ養殖と仲買をしていた父親の手伝いを始めた経歴の持ち主で、漁業へのこだわりは強い。今は海事工事に携わりクレーン船の操船をしているが「漁業ができるような環境になれば、ぜひもう一度漁業に戻りたい」と願っている。
安岐さんの脳裏には産廃投棄現場のかつての風景が焼き付いている。「ツツジの花見が終わって夕日が沈むころ、あたりの山はピンク、緑に染まりました。トンギリ山(魚見山)から見ると海全体が金色に光っているのです。海辺でアサリを採って空いた弁当箱に入れて家に帰りました」。
当初から住民運動の中心人物の一人として産廃問題に取り組んできた安岐さんが「豊島が目指すものは環境の保全ではなく、原状回復なんです」と主張する原点は、子どものころの記憶にある美しい風景である。
■8月から本格処理へ
8月から始まる産廃撤去は、直島の「豊島廃棄物等中間処理施設」に10t積みのコンテナで1日36台(フェリー2往復)で搬出する。公害調停に基づき2028年までに終了することになっている。産廃は焼却・溶融炉に入れて1,200-1,300度で処理し、中に含まれる重金属やダイオキシンを無害化する。処理量は1日200t。処理後にできる溶融スラグはコンクリートの骨材、アスファルト舗装の路盤材になる。飛灰は年間約6,000tを三菱マテリアル直島精錬所で処理する。総事業費は490億円といわれている。

工事中の産廃中間保管施設など
これまでの過程には地元自治会の産廃投棄現場買い取り、産廃排出事業者の「解決金」拠出、さらに資源循環型社会を目指す直島のエコタウン事業と、前例のない産廃問題解決への取り組みがあり、国民の関心が集まっている。
「流れ」は着実に終着点に向かっているが、ここまで問題をこじらせた「張本人」である香川県に対する不信感はくすぶり続けている。当初県は住民の悲痛な訴えに耳を貸さないばかりか、逆に処理業者サイドに立って数々の失政を繰り返した。やっと2000年に県の責任を認めて住民に謝罪した真鍋武紀知事も翌年、豊島問題の責任者といわれる元環境保健部長を「功労者」として環境大臣表彰に推薦し、非難を浴びた。
四半世紀にわたり「古里の美しい島を取り戻したい」と社会正義を叫びつづけてきた住民が3年前に採択した「豊島宣言」。美しい瀬戸内海の自然と調和する元の姿に戻すよう、行政と住民が協力して新しい価値をつくり出す「共創」の理念をうたいあげている。住民会議代表議長の砂川さんは「島の復興には、一次産業の見直しが重要になってくるでしょう」と、農業や漁業の活性化に期待する。
取材途中に自転車で一周した島のあちこちに痛々しい傷跡を見た。建設骨材として安山岩を切り出して消えてしまった山の跡、関西空港埋め立て用土砂の採取跡に産廃と建設残土が運び込まれた場所など、都会のゴミ捨て場になっている瀬戸内海の現実があった。一次産業復活の条件となる豊島の自然再生には、まだ長い時間が必要なようだ。
参考:
豊島“産廃調停”25年 循環型社会への道のりは 初回放送日:2025年6月5日
https://www.nhk.jp/p/ts/X67KZLM3P6/episode/te/1G46WVKLVP/
豊島・島の学校 豊かな島と海を次の世代へ
吉田光宏の執筆記事一覧はこちら