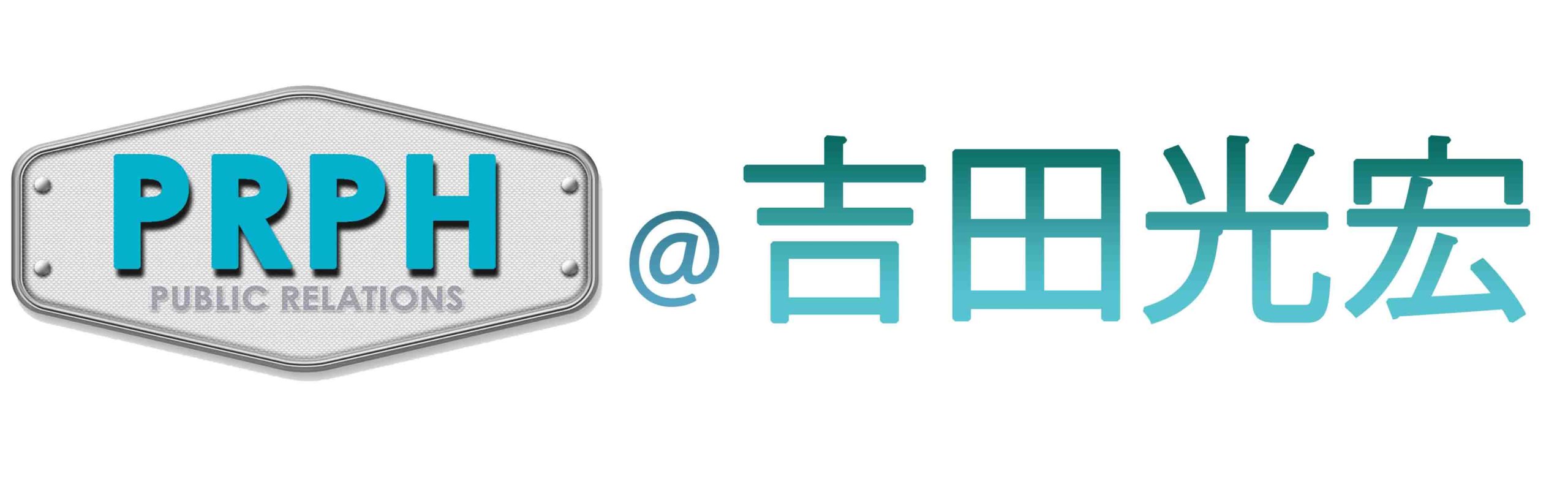すんばらしかった三陸海岸&下北半島
月刊環境情報誌「グローバルネット」の「日本の沿岸を歩く」取材で岩手県三陸海岸、下北半島を訪ねた。全行程7日間。例によってタイトなスケジュール。その甲斐もあって収穫は多かった。取材にご協力いただいた方々には、心から感謝します。
ほぼ1年前から計画したルートは、神戸空港⇒花巻空港⇒盛岡⇒釜石⇒陸前高田⇒宮古⇒八戸⇒大間⇒平内⇒八戸⇒青森⇒神戸空港。鉄道はJR、三陸鉄道、青い森鉄道を使い、釜石、久慈、八戸ではレンタカーを利用した。
旅行中、雨は最初だけで、概ね好天に恵まれた。訪問先の風景や情報を事前にGoogle map で入手できるのだが、現場に足を運ぶと驚きの何と多いことか。東日本大震災からの復興、美しい海岸線と海が印象的だった。

奇跡の一本松
取材前に吉村昭の『三陸海岸大津波』『魚影の群れ』を読んだし、原稿にまとめる過程でさらに情報収取もした。戊辰戦争で敗れ消滅した会津藩が下北に新たに作った斗南藩にも関心を持った。
取材の始点は花巻空港から向かった盛岡。盛岡駅の前にある啄木の歌碑「ふるさとの山に向ひて 言ふことなし ふるさとの山はありがたきかな」。
北上川の開運橋周辺を散策。盛岡城も周辺を歩いた。
<釜石>
盛岡から釜石まで東北本線、釜石線の旅。柳田國男の「遠野物語」の舞台遠野駅を通過。鉄と魚とラグビーで知られる釜石。駅の前にある日本製鉄(株)北日本製鉄所釜石地区の建物に歓迎メッセージ。近代製鉄業発祥の地で「北の鉄人」新日鉄釜石ラグビー部を生んだ。
釜石市魚市場の「魚河岸魚市場」(2017年完成)は最新鋭の衛生管理が自慢だ。周辺にはレストランなど楽しそうな場所がいくつもあった。
南に走り、早朝の高田松原津波復興祈念公園で「奇跡の一本松」を見た。生々しい被災の爪痕や昔の松林の姿を知って、復元への思いに頭が下がる。
再び釜石駅前に戻る。「駅前橋上市場 サン・フィッシュ釜石」が朝7時から営業している。名前はかつて橋の上で営業していた名残りだとか。魚介類、肉野菜などを売り、調理スペース「みんなのキッチン」など、地魚を楽しむためのスペースがある。

駅前橋上市場 サン・フィッシュ釜石
<宮古>
釜石から三陸鉄道で北へ1時間半。宮古駅に到着して宿泊。翌日、三陸海岸で最大の重茂(おもえ)半島の重茂漁港へ向かった。沖は親潮と黒潮が交錯する豊かな漁場だ。取材先は重茂漁業協同組合。ワカメやコンブの養殖、採介藻漁業、定置網漁が中心で、加工事業や直売所も持つ。ワカメの生産量全国一の漁協。水産体験交流館「えんやぁどっと」を訪れ、「重茂産肉厚わかめ」など人気商品を知った。

水産体験交流館「えんやぁどっと」
経営理念としている「天恵戒驕(てんけいかいきょう)」に大変興味を持った。天の恵みに感謝し、おごることを戒め不慮に備えよ、という意味だ。自然環境に配慮した長年の漁業は好業績であり、SDGsの取り組みとしてふさわしいと思った。
岩手県立水産科学館、田老地区(旧田老町)の震災遺構「たろう観光ホテル」なども訪れた。

たろう観光ホテル
<久慈>
三陸鉄道の車窓から沿岸を眺めながら久慈駅に到着。魚市場は休日で、早朝の久慈港周辺を見て回った。日中に集魚灯を使わずにイカを釣る「久慈の昼イカ」漁の漁船もいた。久慈港近くのJC公園内に「東日本大震災モニュメント・ケルン・鎮魂の鐘と光」がある。

三陸鉄道
久慈市は「北限の海女」をテーマにした朝ドラ「あまちゃん」(2013年)で脚光を浴びた。海岸線を走り小袖海女センターへ。観光案内所で海女の展示などを見てドラマの場面がよみがえってきた。

小袖海女センターの展示
あまちゃんオープニング(ロングバージョン)
https://www.youtube.com/watch?v=-UCdRXtAZ6g
南の普代村へも足を伸ばした。巨大津波から村を守った太田名部防潮堤(高さ15.5m)と普代水門(高さ15.5m)を訪れた。太田名部防潮堤に「東日本大震災 津波到達高 11.6m」を示す看板がある。三陸海岸の景勝地、北山崎なども回った。
あまちゃんでもモデルとして登場した種市高校も訪れた。午前8時に流れる『南部ダイバー』(作詞作曲:安藤睦夫)は。潜水士の誇りを感じさせる。海洋開発科で行われた伝統の「南部もぐり」卒業生は海洋工事全般に関わる潜水士として、国内外で活躍している。

種市高校の潜水訓練
<大間>
夜八戸に到着すると、レンタカーで出発した。朝一番で恐山。日本の三大霊場(比叡山、高野山、恐山)全てを訪ねたことになる。戊辰戦争に敗れた会津藩は領地を没収され、斗南藩として再興された。その斗南藩の墓地もあった。

恐山
下北半島の北東端、尻屋埼から本州最北端の大間崎へ。有名な一本釣りモニュメントは、1994年に釣り上げられた440㎏の超大物がモデル。沖の海と空の間に北海道の島影が見える。

マグロの一本釣りモニュメント
大間の「まちおこしゲリラビジネス」を掲げる(株)Yプロジェクトを訪ねた。代表取締役の島康子さんは熱い地元愛を持つ「マグ女」(マグロ女子)。「マグロ一筋」のロゴ入りブリーフ「マグブリ」を買った。身に着けるとマグロが暴れだしそうだ。
下北半島の西側も見なければ。海峡ライン(国道338号)を走り、下北半島の西側を走った。海峡ライン(国道338号)では、景勝地の仏ヶ浦の遠景を堪能。カーブと上下する道に津軽海峡と津軽半島の絶景が伴走する難路に、北限のニホンザルの母子が出現する一幕もあった。
<平内>
下北半島から陸奥湾に出っ張った夏泊(なつどまり)半島へ向かった。平内(ひらない)町漁業協同組合が管理運営する「ほたて広場」を取材した。「青森ほたて」の販売とPRをしている。ホタテガイ養殖の写真や模型などの展示、ホタテガイの販売もしていた。漁協が開発したホタテガイ入りの冷凍ピラフを購入し、特別に電子レンジで解凍してもらって食べた。うまかった!

殻付きのホタテガイ
「夏泊ほたてライン」を巡ると、平内町漁協浦田支所にホタテガイ養殖発祥の地の碑。平内町漁協本所を訪ねると、敷地にある合併五十周年記念碑に「ほたて養殖は始まりあって終りなし」と養殖への意気込みが示されていた。
半島東側の小湊で生まれたのが津軽三味線の名人・高橋竹山(本名高橋定蔵)。竹山をモデルにした『風雪ながれ旅』(歌:北島三郎、作詞:星野哲郎、作曲:船村徹)がさらに好きになる。
北島三郎 「風雪ながれ旅」
https://www.youtube.com/watch?v=cGR3Uu079hQ
<八戸>
取材先の最後は八戸漁港。特に重要な漁港である特定第三種漁港(全国に13港)の一つ。かつて水揚げ量日本一の記録を持つが、近年水揚げ量が減少している。第二魚市場で競りが始まった。赤いフルーツのようなホヤ、ヒラメ、タコの白子、北日本に多いクロソイなど。多彩な魚の面々だ。

八戸漁港の水揚げ
八戸漁港から南へ進むと種差(たねさし)海岸。途中の蕪島(かぶしま)はウミネコの繁殖地(国の天然記念物)。蕪島から福島県相馬市松川浦まで1,025㎞は「みちのく潮風トレイル」がある。
再び北へ進路をとると小川原湖(おがわらこ)に到着。青森県で一番大きい湖で汽水湖。かつてイトウ が生息していたという湖は、ワカサギ、シラウオ、ハゼ、ヤマトシジミ、ウナギなど水産資源が豊富。同じ青森県の十三湖に比べると知名度はいま一つだが、教えてもらった店で味わったシジミ汁はうまかった。
20250927 revised